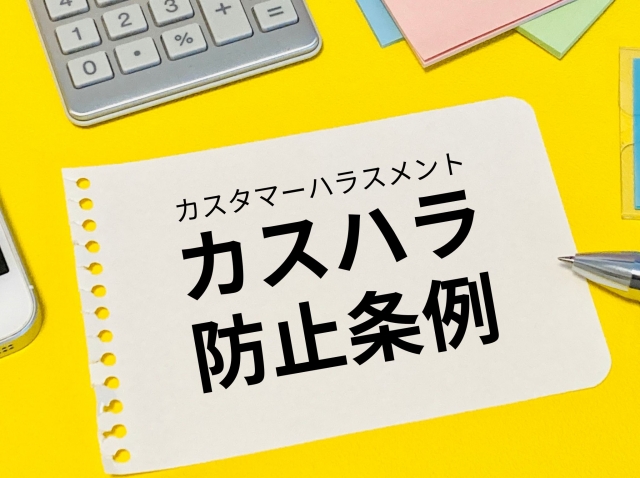あっというまに10月も半ばに来てしまいました。先週末は無事に秋祭りも終わり、一気に秋が深まっていくというか、年末に向けて加速していくように感じます。今日は、先月末に参加した研修の話です。9月は2回カスハラセミナーを受講しました。
①なぜ今カスハラ対策が注目されているのか
先日、兵庫県社労士会・西脇支部の研修に参加しました。テーマは「カスハラ対策」。同じ9月には姫路支部でも同テーマの研修が開かれており(先日のブログはこちら)、いま大きな関心を集めています。その背景にあるのが、2026年から企業におけるカスハラ対策が義務化されるという流れです。
厚生労働省が2024年5月に発表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間で勤務先でカスハラを受けた人は10人に1人という結果が出ています。カスハラによって従業員の心身の健康が損なわれるリスクは高く、企業としても無視できない問題になっているのです。
②カスハラの定義と法的な位置づけ
「カスハラ」という言葉は耳にする機会が増えましたが、法的に明確な定義があるわけではありません。厚労省が2022年に発表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、次のように整理されています。
- 顧客からのクレーム・言動で、
- 要求の内容の妥当性に照らして、
- その手段や態様が社会通念上不相当であり、
- 労働者の就業環境が害されるもの。
つまり「不当な要求や過剰な言動で、働く人の環境を壊す行為」がカスハラとされます。ここで重要なのは、単なるクレーム対応の延長ではなく、従業員を守るべき安全配慮義務に関わる問題だという点です。もし企業が対策を怠れば、損害賠償責任を負う可能性もあります。
実際に、今年に入ってからは役所で働く人を守るためのカスハラ防止条例が相次いで制定されました。東京都や北海道では2025年4月1日から、徳島県牟岐町や愛知県では10月1日から施行される予定です。公的機関から始まった流れは、今後民間企業にも確実に広がっていくでしょう。
③企業に求められる取り組みと課題
では、企業はどのようなカスハラ対策を取るべきなのでしょうか。厚労省のマニュアルでは、以下の4点が基本的な対策として示されています。
- 基本方針を明確にし、従業員に周知する
- 相談体制を整備する
- 対応方法や手順を策定する
- 従業員への教育を行う
ただし一口に「カスタマー」と言っても、業種ごとに顧客の特性は大きく異なります。ホテル、飲食、小売、医療、金融…それぞれにカスハラの出方は違います。パワハラやセクハラのように「一律のルール」を作りにくいのが特徴です。そのため、自社のビジネスモデルに合った具体策を練ることが欠かせません。
これからの時代、企業は「お客様は神様」という従来の発想から一歩踏み出し、従業員を守ることも経営リスク管理の一部と捉える必要があります。制度が義務化される前に、早めに取り組むことが大きな安心につながります。
カスハラ対策に関するご相談は、ぜひハルカゼまでお問い合わせください。ホテル支配人16年の経験を持つ社労士が、現場感覚を交えたアドバイスでサポートいたします。
<おすすめ!採用支援メニュー>
ソーシャルリクルーティング実践塾(兵庫県経営革新計画承認事業)はこちら
<セミナーメニュー>
顧問契約に関わらず対応します。SNS発信、採用支援が得意です!
<SNSアカウントのフォローお願いします!>
平日朝8:30~ インスタライブ、TikTokライブ、standFMで同時配信やっています。
Instagram (平日朝8:30~ インスタライブしています)
https://www.instagram.com/harukazekun_sr
X(日々の出来事、最新のお知らせ)
https://twitter.com/kanba_sr
TikTok
https://www.tiktok.com/@harukaze2023
YouTube(採用支援について発信しています)
https://www.youtube.com/@harukaze2023